結論から言うと、大変面白い本だった。
もともと絵画本体というよりも、絵画と社会との関わりの方が興味があるし、また絵画とはそういやって見るものだと思っているので、そういう意味で大変満足のいく一冊だった。
今までは自分の興味のあった時代しか、そういう観点で見ていなかったけれども、本書でダイジェストのようにざっと見れて、そういう意味では全体的に概要を見るためにもってこいな1冊だったと思う。
絵もカラーで見れるので大変分かりやすかった。
できたら手元に置いておきたい1冊だった(図書館で借りたので…)
とりあえず目次を抜粋しておくと;
第1章 西洋美術の発祥 ~古代ギリシアから中世への旅~
古代ギリシアから中世までの美術の変遷を、ひと味違う視点で解説。
ギリシアの彫刻たちが語りかけてくる内容に耳を傾けてみると…。
『幼児ディオニュソスを抱くヘルメス』、『サモトラケのニケ』、
『ラオコーン』、『ミロのヴィーナス』、『皇族の行列』、
シャルトルのノートル・ダム大聖堂、ランスのノートル・ダム大聖堂など。
第2章 フィレンツェに咲いたルネサンスの華
経済が発展し、生活レベルが一気に向上した13~15世紀のイタリアで、
古代ギリシア・ローマの文化と芸術が復活。キリスト教とそれらが
どう折り合いをつけていったのか、ルネサンスの本質に迫ります。
ボッティチェリ『プリマヴェーラ(春)』、
ロッセリーノ『レオナルド・ブルーにの墓廟』、
ミケランジェロ『聖家族』、ラファエロ『アテネの学堂』、
マンテーニャ『聖セバスティアヌス』など。
第3章 神の名のもとに ~キリスト教絵画の変容~
15~17世紀、ネーデルランドではプロテスタントの台頭に伴い、
宗教絵画が劇的に変化します。
この面白さがわかったら、あなたももう美術通!
カンピン『メロードの祭壇画』、エイク『ゲントの祭壇画』、
ウェイデン『十字架降下』、フース『ポリティナーリの祭壇画』、
ボス『愚者の船』『快楽の園』、デューラー『自画像』『四人の使徒』、
アールツセン『肉屋の店先』、ブリューゲル『狩人たちの帰還』『盲人の寓話』、
レンブラント『眼を潰されるサムソン』『キリストの説教』など。
第4章 フェイス ~肖像画という名の伝記~
肖像画に隠されたメッセージを読み解くと、思わぬ素顔が見えてきて。
エイク『アルノリフィニ夫婦の肖像』、
ダ・ヴィンチ『モナ・リザ』、クリーエ『フランソワI世』、
ホルバイン『ヘンリー8世』、リュベンス『マリー・ド・メディシスのマルセイユ上陸』、
ダイク『狩場のチャールズI世』、ブーシェ『ポンパドゥール夫人』、
ルブラン『マリー・アントワネットと子どもたち』、
ダヴィッド『サン=ベルナール峠を越えるボナパルト』、
げーんズボロ『ロバート・アンドルーズ夫婦』など。
第5章 天使からのメッセージ ~天使はキューピッドではない!~
天使とキューピッドの違いを徹底解剖。「へえ、そうだったんだ」の連続です。
ジェラール『アモルとプシュケ』、
パルミジャーニ『弓を作るクピド』、
ラファエロ『ガルテイア』『サン・シストの聖母』、
リュベンス『愛の園』、ベリーニ『赤いケルビムの聖母』、
ダ・ヴィンチ『受胎告知』、
ボッティチェリ『聖母子と八天使』、
スルバラン『大天使ガブリエル』、
プーサン『聖母被昇天』など。
第6章 人生の喜び ~オランダ絵画の魅力~
17世紀のオランダはバブルだった!? そこで流行した風俗画の魅力をご紹介。
ハルス『陽気な酒飲み』『マッレ・バッベ』、
レイステル『フルートを吹く少年』、
ステーン『聖ニコラウス祭の前日』、
フェルメール『女主人と召し使い』『士官と笑う娘』など。
第7章 エデンの園からの追放 ~風景画の始まりと変遷~
宗教画の背景にすぎなかった風景が、“風景画”として独立し、
発展してきた過程とは?「風景画は奥が深い」と納得です。
ランブール兄弟『ベリー公のいとも豪華なる時禱書』、ヴィッツ『奇跡の漁り』、
アルトドルファー『イッソスの戦い』、パティニール『三途の川を渡るカロン』、
ホイエン『二本の樫のある風景』、ロイスダール『ユダヤ人墓地』、
ロラン『アポロとクマエの巫女のいる海辺』、カナレット『大運河の眺め』、
ローザ『壊された橋のある風景』、カンスタブル『乾草車』、ターナー『奴隷船』、
コロー『湖』、ブータン『トルーヴィルの浜辺』など。
第8章 印象派登場 ~モダンアートの始まり~
印象派はなぜ登場したのか。
きれいなだけではない印象派の真髄に迫ります。
クールベ『オルナンの埋葬』、マネ『オランピア』、モネ『印象、日の出』、
バジール『家族の集い』、ルノワール『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』
『シャルパンティエ夫人と子どもたち』、ピサロ『イタリア大通り』、
ドガ『アブサン』『プリマ・バレリーナ』、モリゾ『海辺の別荘』、
カサット『果物をつむ二人の若い娘』など。
木村泰司 「名画の言い分」 2007年 集英社
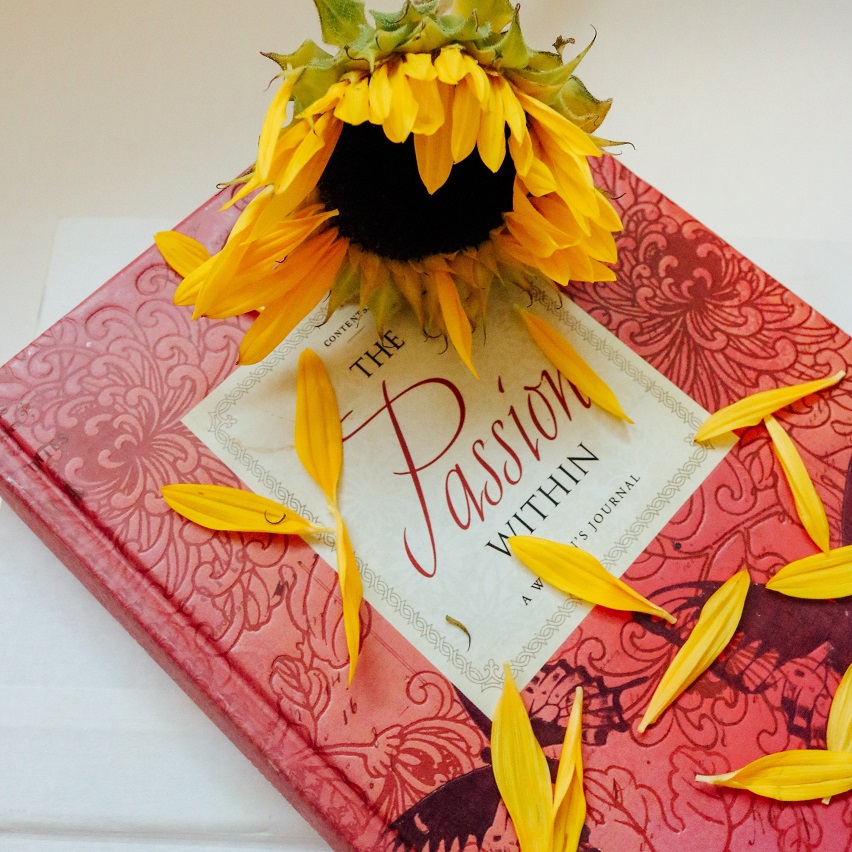

コメント